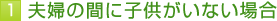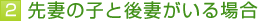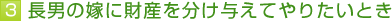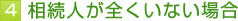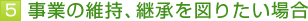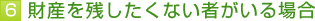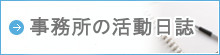遺言で何が出来るのか
遺言で何が出来るのか
法律が遺言事項として定めているのは、次のような内容になります。
- 遺贈(民法第964条)
相続権のない者に財産を残したい場合、例えば、とても世話になった長男の妻になんらかの配慮をしたい場合は、遺言が必要になります。 - 相続分の指定(民法第902条)
被相続人が遺言で相続分を指定したとき(「○分の○」、「○%」)は、これが法定相続分に優先することになります。(遺言以外では相続分の指定はできません。) - 遺産分割方法の指定(民法第908条)
遺産分割方法の指定とは、例えば妻には不動産、長男には〇〇銀行の定期預金、次男には〇〇株式会社の株式2万株というように、誰に何を相続させるかを具体的に指定することをいいます - 遺産分割の禁止(民法第908条)
- 相続人の廃除・その取消し(民法第893条・民法894条)
- 遺留分減殺方法の指定(民法第1006条但書)
- 寄附行為(民法第41条2項)
- 認知(民法第781条2項)
- 後見人・後見監督人の指定(民法第839条・民法第848条)
- 遺言執行者の指定又はその指定の委託(民法第1034条)
- 祭祀主宰者の指定
- 葬式の方法等の指定
遺言が特に必要な場合

ある程度の財産がある場合は、遺言が必要と思われますが、以下のようなケースについては特に必要と思われます。
子供がいない場合に夫が先に死ぬと、妻が全財産を相続できると思っている人がいますが、夫に兄弟姉妹があれば、妻の相続分は3/4で、1/4は夫の兄弟姉妹にいくことになります。そこでこの場合に、夫が「全財産を妻に相続させる。」と遺言しておくと、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言通りに全財産が妻にいくという大きな効用があります。
先妻の子と五歳との間では、血縁関係がなく、感情的になりやすいので、遺言できちんと財産分けの指定をしておくことが、遺産分割時のトラブル防止に役立ちます。
長男が死亡した場合で、長男の妻が亡き夫の親の世話をしている場合、長男の妻は相続人ではないので、遺言をせずに親が死んでしまうと、遺産は亡き夫の兄弟姉妹が相続し、長男の妻は何ももらえないことになります。(場合によっては、家を出て行かなくてはならないことも考えられます。)この様な場合を想定し、あらかじめ便宜を図っておくのであれば、遺言で相応の財産を長男の妻に遺贈しておく必要があります。
この場合には、遺産は特別な事情がない限り国庫に帰属することになります。そこで、親しい人やお世話になった人にあげたいとか、お寺、社会福祉法人などに寄付をしたいといった場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
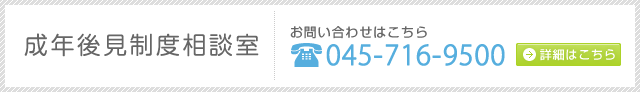 行政書士:佐藤浩史が担当しております。
行政書士:佐藤浩史が担当しております。